介護士(および元介護士)八名による職業詠の短歌ネプリ企画「ハレとケア」に参加しました。
今回は、「ハレとケア」に掲載されている作品への個人的な感想と、企画全体への感想を書き残したいと思います。
短歌についての感想
「ハレとケア」は八名の参加者がそれぞれ五首を詠み、計四十首が掲載されたネプリ企画です。
各参加者の作品のなかで特に好きだった一首を引用します。
一ノ瀬美郷さん
同じことばかり尋ねてくる人の瞳の地獄と目が合っている
一ノ瀬 美郷
介護士=認知機能が低下した高齢者を支援する仕事というイメージを持っている方は多いはず。作中主体だけでなく、多くの介護士はその瞳を見たことがある。「ここはどこ?」「いつ帰れる?」「これからどうしたらいいの?」そう尋ね続ける被介護者の不安に対して、どう支援していくのかを考え続ける仕事でもある。
地獄は被介護者だけでなく、目が合っている作中主体の瞳にも存在する。
救いを求め尋ねる地獄と、尋ね続けられる地獄。
被介護者の瞳を通して、自分が地獄と感じている部分にも気づいてしまうのだろう。ドキリとさせられる。
この作品はネプリの右上、一首目に配置されている。
介護士職業詠の入り口としても良い作品だと感じた。
ホワイトアスパラさん
忘却の森にあなたが迷うからパン屑として言葉を落とす
ホワイトアスパラ
暗く霧の濃い森にその人はいる。作中主体が「あなた」を森から連れだせるなら話は早いが、それは難しい。介護士の仕事はなんでもやってあげられる仕事ではないし、どんな人でも落ち着かせる魔法も存在しない。制限やしがらみがあるなかで支援し続ける仕事だ。
作中主体が言う言葉の「パン屑」は、ヘンゼルとグレーテルをモデルにしたもの。被介護者が忘却の森から無事に帰ってこられるように、道しるべを作っている。ヘンゼルとグレーテルが落としたパン屑は小鳥に食べられて消えてしまう運命にある。私たちが忘却の森に落とす言葉も、たいていは消えてしまうのだろう。それでも道しるべを落とし続ける行為は、祈りにも似ている。消えると知っていても、私たちは続ける。
六浦筆の助さん
介助者の腕白樺にする婆よ いくら搔いても蜜は出ないよ
六浦筆の助
白樺は落葉樹。被介護者である高齢者の女性が、介助者の腕をまるで猫が爪とぎをするように引っ掻いている。
その場面を想像すればかなり衝撃的な1シーンなのだが、作中主体はどこか余裕があって、ユーモラスに「蜜は出ないよ」なんて言ってしまっている。これは被介護者が日常的に同様の行為を繰り返していて、介護者からしたら「はいはい、またか」という呆れ/慣れの気持ちになっているようにも読めた。
介護士による高齢者虐待のニュースは取り上げられても、その逆を取り上げられることは稀。
実際、介護士が被介護者から暴力を受ける場面は多々ある。面白さの先に、介護士の仕事のリアルさが見えてくる一首だ。
涸れ井戸さん
素潜りのような夜勤で真珠とは程遠い宝物を探す
涸れ井戸
素潜りでの漁は命がけ。命を賭けられるのはそれが伝統的で価値のある行いであったり、真珠という宝物があるから。
介護士の夜勤は二交代制なら十六時間労働。
長時間労働のうえ、たくさんの利用者の命を預かっている仕事なので、素潜りと表現する気持ちにも共感できる。
介護士は夜勤でなにを探すのだろうと考えたとき、候補はたくさん出てくる。「利用者がなくした義歯」だったり、「どこかに落とした薬」だったり。ときには存在しないものを一緒に探し続けることもある。世間一般で言う直接的な支援(排泄介助や入浴介助)以外にも、なにかを探す業務は突発的に発生する。
真珠のような宝石ではないけれど、義歯や薬は利用者の日常を繋ぐ大切な宝物でもある。
限られた人材と限られた時間のなかで、私たちは宝物を探すのである。ほど遠くても、宝は宝。
非常口ドットさん
便を拭き遺体に触れたその腕は茶碗を持って赤子を抱く
非常口ドット
介護士は「けがれ」に触れることが多い。
汚れもあれば穢れもある。エンゼルケアでは同時に触れることもあるだろう。
その腕の持ち主にも生活(食事)があり、守るべき存在(赤子)がプライベートにも存在する。
どこか「介護士」という存在は画一的に見られる部分が多い。
優しくて当然、しんどくて当然、自分のすべてを賭けて利用者と向き合うのが当然……だとでもいうような。
この歌は介護士という職業の奥にいる、ひとりの人間を再認識させてくれる奥深さがある。
けがれがあったとしても、尊ぶべき腕だ。
aurora/小野小乃々さん
事業所をたためば春めくスカートを一週間に八日穿きたい
aurora/小野小乃々
「たためば」とあるので、作中主体は事業所の運営側にいる介護士だと思われる。居宅介護支援か、訪問介護なのか、通所系なのか、それは短歌からは読めない。どれにせよ、支援の中でスカートを穿きながらできるような業務はほぼない。
運営側にいるということは、関わるのは利用者だけではない。利用者の家族、他サービスの関係者、事業所のスタッフ……そのどれからも負担を掛けられる場面が出てくる。作中主体のストレスや、抑圧されている感情。そこからの解放を「スカート」という自由にひらめくものに託しているように私は読んだ。スカートを「週七日」ではなく「週八日」だとしてるのも効果的になっている。実際は週に八日もスカートは穿かない。そんなのは絵空事であると、作中主体は自分でもわかっている。だからこそ「諦め」を感じるし、歌に説得力が出る。
薊桜蓮さん
真っ黒なミイラと化した足を保つ汝は手でなお吾の手を払う
薊桜蓮
被介護者は助けを求めている方ばかりではない。ごみ屋敷に住んでいる方が掃除を望んでいる方ばかりではないように、命がぎりぎり繋ぎとめられているような状況でも、支援を断る方がいる。
「真っ黒なミイラ」と表現された被介護者は、数か月単位で入浴できていない状況で、栄養状態も悪いのかもしれない。「そんな人いるの?」と思うかもしれないが、存在する。そのような状況でも人の手を払う力が残っているのだから驚きである。同時に、自分ならちょっとだけほっとするかも。元気な部分があることに救われるので。
介護士は手を振り払われることはできても、振り払うことはできない。
何度も何度も手を差し伸べ続ける切実さを感じる歌だった。
企画全体を通しての感想
正直に話すと、介護……特に介護観について人と語り合うのは好きじゃありません。
介護観というものはかなり複雑な形をしています。教科書的な定義があって、そこにそれぞれの信念やプライド・理想が乗っかっています。利用者への個別性を大事にしているからこそ、議論が生まれやすくなっているんです。だから語ろうとするとケンカになったりするし、話せば誰かが不快になることもある。少なくとも私はそう思っていて、安易にSNSで介護観を発信しないようにしていますし、積極的にそのような呟きを見ることもしていません。
今回の「ハレとケア」では、短歌というフィルターを通してそれぞれの作者の介護観に触れました。触れましたが、嫌な感情だとか否定する気持ちは、驚くほどに湧きませんでした。短歌を通すことで、よりその場面・感情・作中主体に寄り添おうという気持ちが生まれてくるからかもしれません。
主催者の非常口ドットさんが、こんなnoteを書いてくれています。
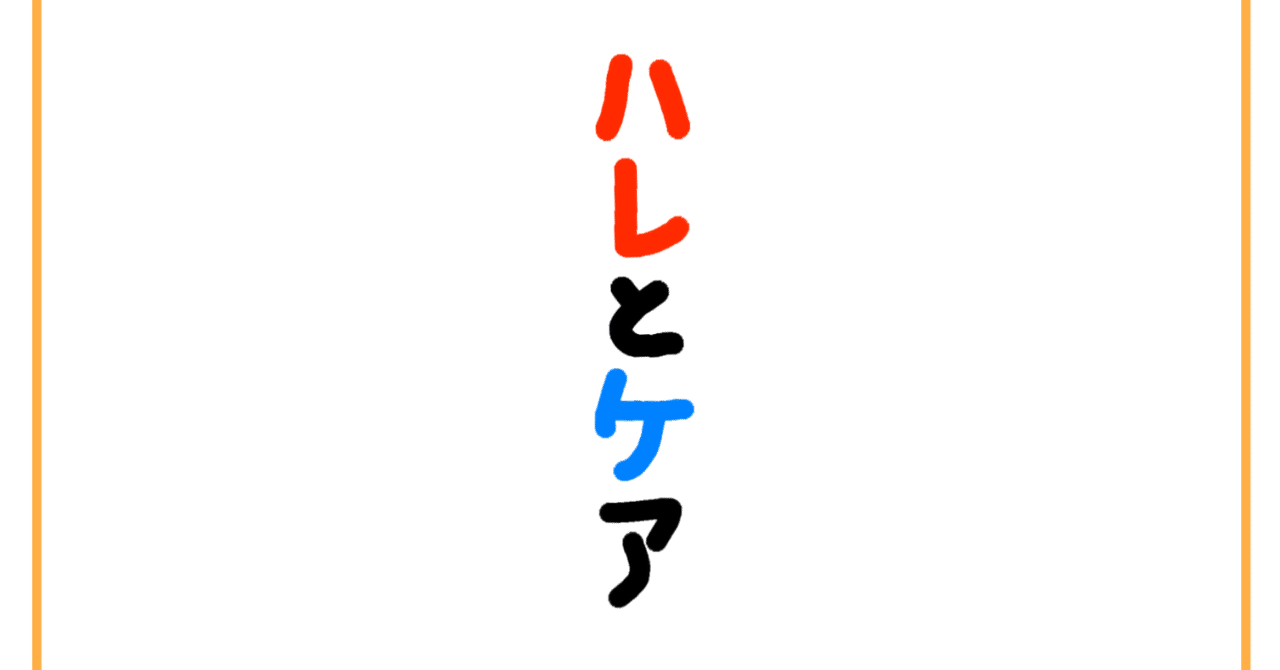
noteの中で「介護業界にとって意義のあること」だと書かれているのですが、たしかにそのような可能性があると思います。
短歌は詠むことで自分と向き合うことができるし、短歌を読むことで他者の介護観に触れることができるので。
「ハレとケア」では現場の光景を詠んだ作品も多いですし、リアルな介護の現場を知る機会にもなるのではないでしょうか。
参加者としても読者としても、大変楽しく読ませていただきました。
最後に、私が寄稿した作品も一首、紹介させてください。
ミルフィーユ 光を重ねゆく日々よ痩せぎすの手にワセリン馴染む
蜂賀三月
素敵な企画にお誘いいただき、本当にありがとうございました。
また、ネプリを印刷して私の作品を読んで頂いた方々にも、深く感謝いたします。
短歌については、今後もマイペースに活動していく予定です!


コメント